-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
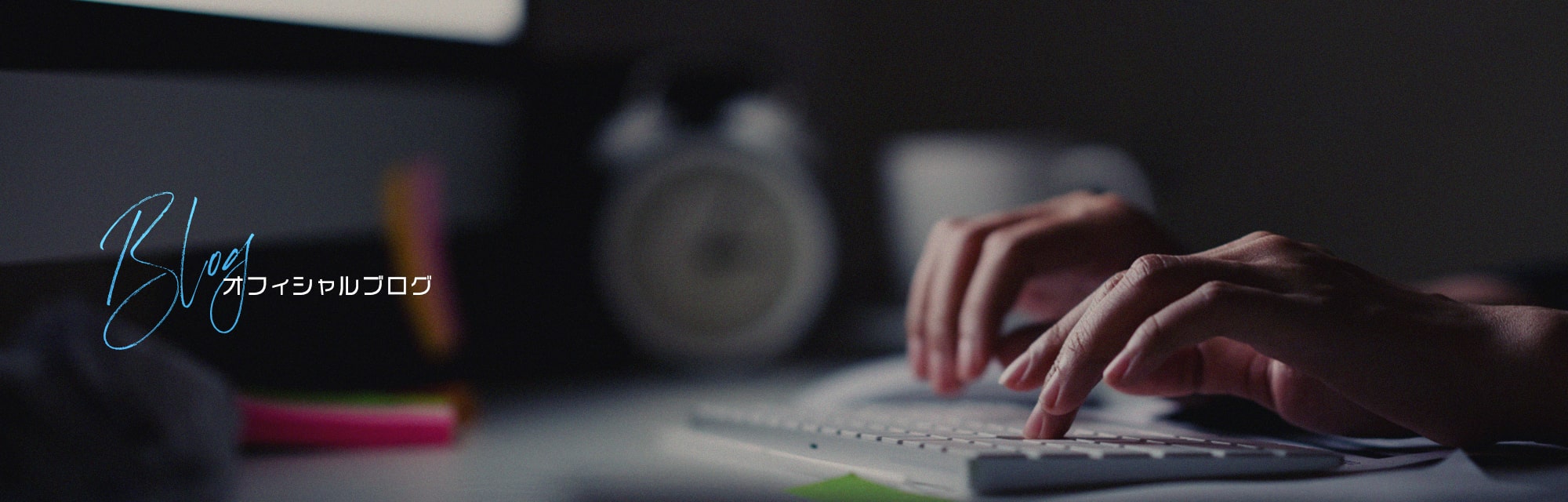
皆さんこんにちは!
合資会社大坪組、更新担当の中西です。
~強い海運~
世界の物流は海が運びます。だからこそ海運には、コスト競争力と環境性能、そしてスケジュール安定の三立が求められます。本稿は、現場で効く「脱炭素と運航最適化」を、燃料・運航・データ・港湾協業の4レイヤーに分けて“実装の順番”まで落とし込んだガイドです。
目次
脱炭素はイメージではなく燃費=コストの話。優先順位は次の通りです。
効率改善(OPEX小・即効性大)
スピードマネジメント(最適速力・スロースチーミング)
船底/プロペラの定期清掃・研磨
トリム最適化・ウェザールーティング
JIT(ジャストインタイム)入港による待機燃料の削減
燃料転換(中期投資)
ドロップイン系:バイオ燃料(混焼で導入容易)
新燃料:LNG、メタノール、アンモニア等(設計・供給網が前提)
設計・装置(CAPEX大・長期)
風力補助(ローターセイル等)、空気潤滑、廃熱回収
新船・改造(燃料仕様、電装・配管刷新)
まずは運航効率で“今ある船”の燃費底上げ → 次に燃料 → 最後に設計。この順に進めると投資効率が高まります。
“速度一定”から“到着時刻一定”へ。
天候・潮流・バース空き状況に合わせ、到着時刻を厳守しつつ燃料極小化を目指す。
船底・プロペラの汚損度をKPI化(燃費悪化率で可視化)。
研磨・洗浄は航路・水温・寄港地に合わせた最適周期で。
積付計画と連動し、波浪・喫水制限を踏まえたトリム設定を標準化。
デッキ上の風圧・波当たりも考慮し、航海中に微調整。
風・波・海流予測を踏まえたウェザールーティングで、燃費と安全余裕を同時確保。
データ粒度:Noon Report(1日1回)から、エンジン・燃料・環境センサの高頻度化へ。
KPI例:
gCO₂/トン・海里、燃費(t/day, t/round)
時間チャーター等価(TCE)、オンタイム率、寄港“窓”遵守率
船底・プロペラ汚損指標、待機時間(沖待ち/岸壁待ちの内訳)
可視化→標準化→例外対応の順で、現場に“効く”運用へ。ダッシュボードは「船・航路・港」の3軸で切ると原因が見えます。
遅れの連鎖を防ぐ要は港での予見性。スロット/窓の見直し、JIT入港の情報連携を。
接岸→荷役→出港の標準作業時間を再設計。
書類・承認プロセスを事前電子化し、岸壁滞在を短縮。
フィーダー・鉄道・トラックの連携で集疎効率を平準化。
コンテナデポの滞留日数をKPI化し、回転率を改善。
バイオ燃料:即導入可、既存主機で混焼。供給と価格が鍵。
LNG:SOx/NOx低減、インフラ前提。メタンスリップ対策が論点。
メタノール:取り扱い容易、エンジン対応が進む。燃費密度は要注意。
アンモニア:将来の有力候補。毒性と燃焼特性に留意、港湾側の準備が必要。
陸電(SSE/OPS):停泊時の排出と騒音を抑制。港の設備状況で評価。
結論:単一解はない。航路・船型・寄港地のインフラを軸に複線で進めるのが現実解。
CAPEXは燃費改善OPEXで何年回収かを明確化。
燃料プレミアム(グリーン燃料の割高分)は、荷主と共有するスキームを早期に整備。
長期契約(COA等)では燃料条項・環境付加価値の扱いを事前に合意。
速力・ETA基準を“到着一定”に切替
船底・プロペラ清掃の閾値と周期を規定
トリム・ドラフトの標準設定表を整備
ウェザールーティングの採否基準(波高・風・回避率)
JIT入港の情報連携(ETA/バース/荷役窓)
KPIダッシュボード(船×航路×港)を週次レビュー
燃料ポートフォリオ(ドロップイン→新燃料)計画
CAPEX回収年数・燃料条項・グリーン価値の契約整備
効率→燃料→設計→協業の順に打ち、KPIで回す。
海運の競争力は、日々の速力と到着、そして岸壁の一時間に宿ります。小さな改善を回し続ける会社が、コストでも環境でも勝ちます。
![]()